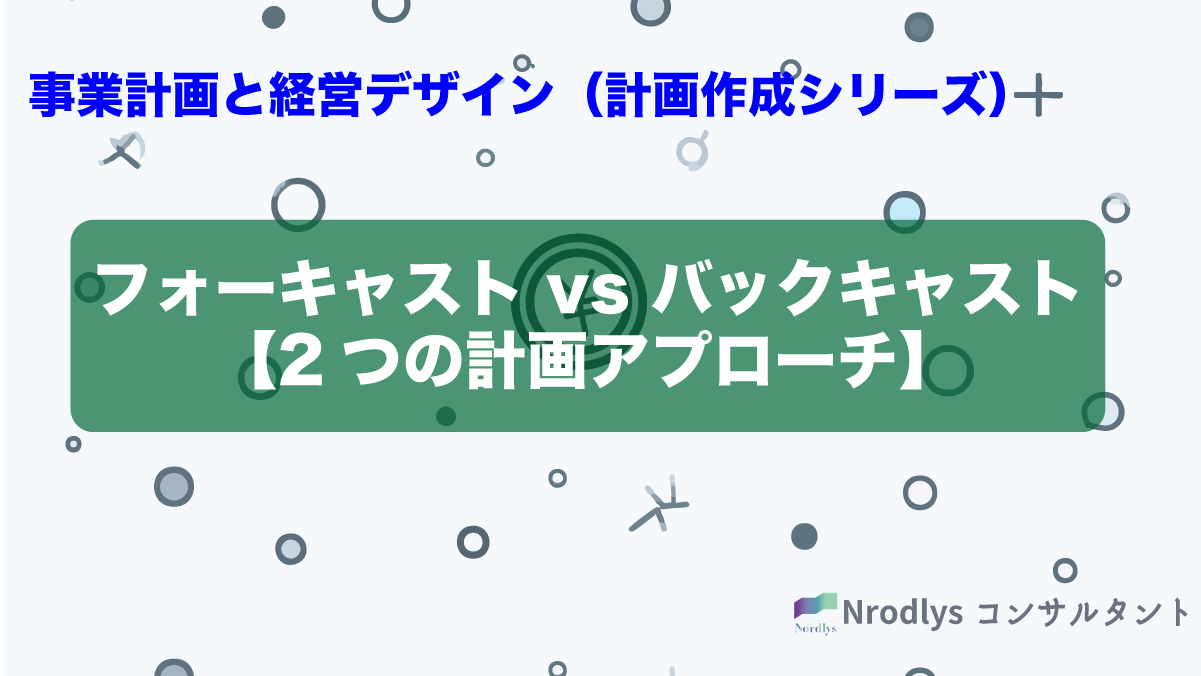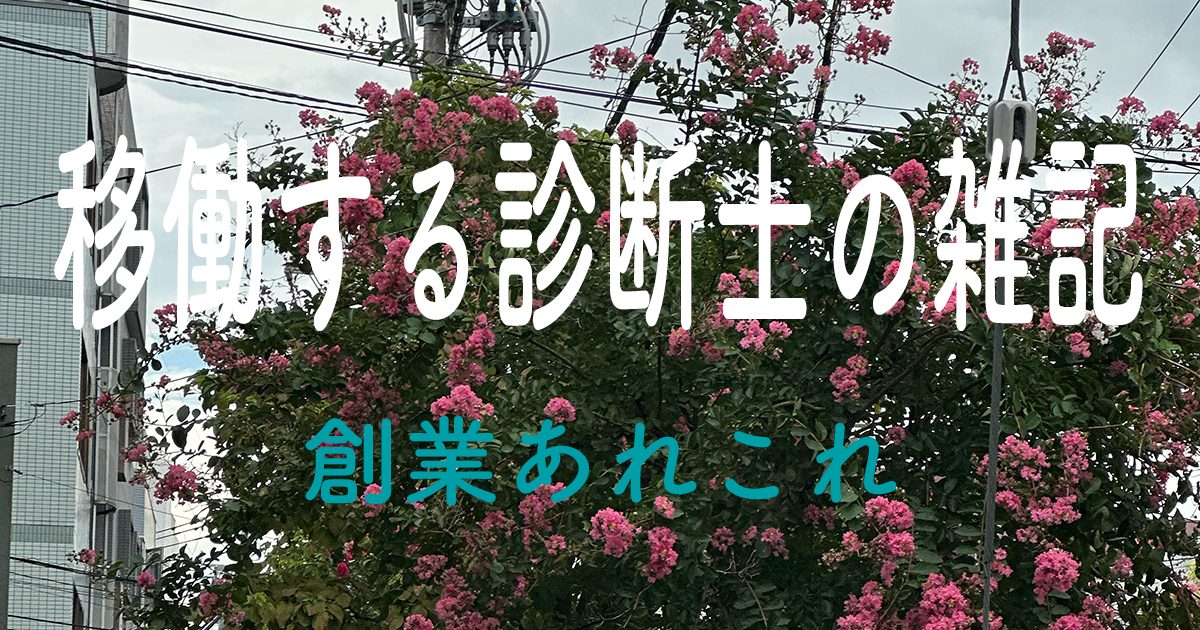事業計画が必要な理由と基本的な考え方
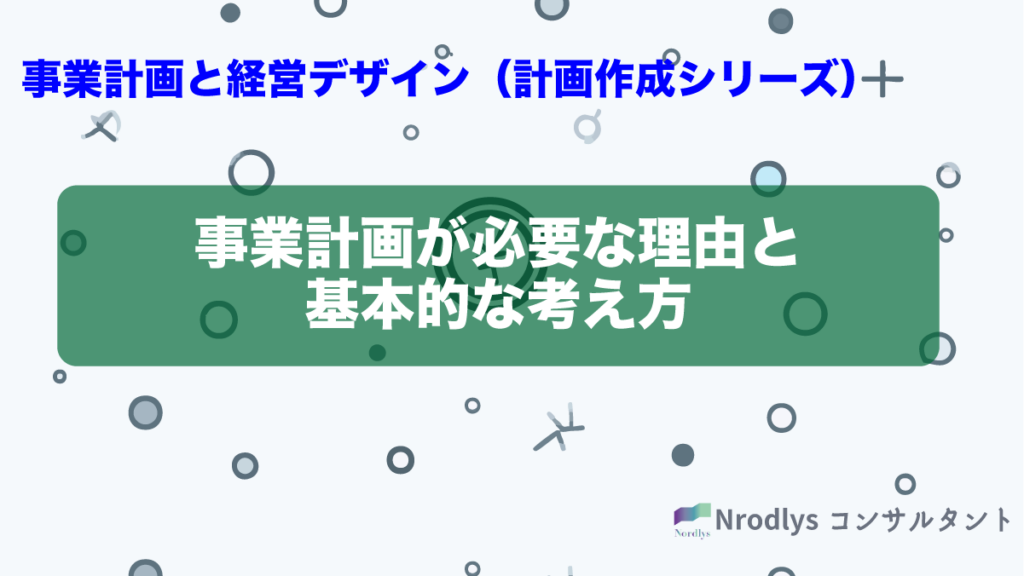
企業を経営しているうえで、「事業計画を作る」と言う局面に出会うことが多くあるかと思います。よくある局面は、創業時、補助金、助成金申請や金融機関への説明のためがあるかと思います。この計画を作る機会を有効に利用してみませんか?
経営者の本音としては「事業計画なんて作っても意味がない」「計画通りにいかないから無駄」と言った声でしょうか?事実、計画通りに進まないことがの方が多いのですが、「事業計画は未来を当てる」ためのものではなく、事業計画を立てる行為に自体に、重要な価値があるのです。
そこで、なぜ事業計画が必要なのか、そして計画作成の基本的な考え方について解説します。
なぜ事業計画が必要なのか
1.考えを整理し、判断基準の拠り所にできる
日々事業を進める中では、多くの判断タイミングがあります。このままで問題ないか?新たな商品、サービスに取り組むべきか?設備投資をすべきか?人を増やすべきか?事業計画があれば、これらの判断に一貫した基準を持つことができます。
計画がない場合、その場の感情や短期的な損得で判断してしまいがちです。しかし、事業計画があることで、判断基準が明確になり「目標に沿っているかどうか?」から冷静に判断できます。
2.ステークホルダーとの認識を合わせられる
事業運営には従業員、取引先、金融機関、投資家など多くの関係者との協力が必要です。これらのステークホルダーと同じ報告を向くための「共通言語」としての役割を事業計画は果たします。
特に、融資を受ける際、金融機関は「この事業者はどこへ向かおうとしているのか?」「返済能力があるのか」を判断する必要があります。この時、事業計画があることで、金融機関の信頼を得やすくなります。
3.リスクについて理解が深まる
事業計画を作るということは、会社の状況を一歩引いてみることでもあります。この時、様々なリスクや課題が見えてきます。「もし、これが起きたらどうするのか?」を事前に考えておくことで、実際に起こった時に素早く対応ができます。
リスクを完全に避けることは不可能ですが、想定しておくことで被害を最小限に抑えることが可能となります。
経営コンサルタントからの視点
よく「計画なんて状況が変わるから意味がないよ」とか「計画作ったけど意味がなかった」と言う声も聴きます。しかし、実は計画策定のプロセスにこそ意味があります。自社の強み・弱み・取り巻く環境などを客観的に分析し、具体的な目標を設定する過程で、経営者自身の思考が整理され、判断力が向上します。専門家は代わりに作るのではなく、第三者視点でそのお手伝いができるのです。
計画策定の基本的な考え方
計画の種類と使い分け
ひとえに計画といっても、目的によって作るべき計画の内容は異なります。代表的な計画の種類を理解しておくと、意味がなかったとはなりにくくなります。
創業計画
初めて事業を起こす時に作成します。全く経営経験がない状態で立てることが多いため、戸惑うことが多いです。事業の概要、市場分析、収支計画、主に融資申請や投資家への説明で使用されます。
中期経営計画
既存事業を主体に、会社をこれから3-5年間でどう発展させるかを描いた計画です。事業拡大や新規事業展開を検討する際に作成します。(大手企業は必ず作っています)
資金調達計画
設備投資や運転資金の調達を目的とした計画です。金融機関への融資申請時に必要となります。また、スタートアップ企業の場合はVC向けのピッチ資料(市場規模や可能性が大切)が該当する場合もあります。誰に提示するかで、内容が大きく変わります。
補助金に伴う事業計画書
補助金・助成金の申請で求められる計画です。おそらく専門家が頼まれる計画書では一番多いのではないでしょうか。それぞれの補助金・助成金の目的に即した計画を定められた内容で作成するものとなり亜伴走支援巣。
よくある誤解
誤解1:「計画通りにいかないから意味がない」
計画の価値は「当てる」ことではなく、「考える」ことにあります。計画を作る過程で得られる気づきや整理された思考こそが重要なのです。
誤解2:「完璧な計画を作らなければならない」
最初から完璧である必要はありません。まずは現時点でわかることを整理し、新しい情報が得られたら随時更新していけばよいのです。
誤解3:「一度作れば終わり」
事業環境は常に変化します。定期的に計画を見直し、必要に応じて修正することが大切です。
計画作成で重要な3つのポイント
1. 現実的な目標設定
高すぎる目標は達成困難で、低すぎる目標は成長を阻害します。基本的には過去の実績や市場環境を踏まえた現実的な目標を設定しましょう。(ただし、飛躍する必要がある場合はチャレンジングな目標を目指せる現実的な目標が必要です)
2. 具体的な数値の設定
「売上を増やす」ではなく「売上を20%増加させる」や、5年後に売上達成1億円とか、顧客月1,000人達成というように、可能な限り具体的な数値で目標を表現します。(なぜその数字なのかの裏付けも大切)
3. 定期的な見直し
計画は「作って終わり」ではありません。状況は刻々と変化するため、定期的に実績と比較し、必要に応じて事業または計画の修正を行いましょう。
事業計画作成の実際のメリット
融資・資金調達での優位性
金融機関は、事業計画の有無とその内容を重視します。また、VCは計画を見て経営者の能力を判断しています。明確な計画があることで、「計画的に事業を進める経営者」として信頼を得ることができ、融資条件も有利になることが多いです。
従業員のモチベーション向上
従業員にとって、自分が働く会社がどこに向かっているのかがわかることは重要です。明確なビジョンと計画があることで、従業員のモチベーションと帰属意識が向上します。
意思決定スピードの向上
日々の業務で迷いが生じた時、事業計画という判断基準があることで、迅速で一貫した意思決定が可能になります。これは、変化の激しい現代のビジネス環境では大きな競争優位性となります。
【次のステップ】より効果的な計画手法を学ぶ
事業計画の重要性と基本的な考え方をご理解いただけたでしょうか。
実際に計画を作成する際には、「フォーキャスト」と「バックキャスト」という2つの異なるアプローチがあります。状況や目的に応じてこれらの手法を使い分けることで、より効果的な事業計画を作成することができます。
この2つのアプローチの違いと使い分けについては、次回の記事で詳しく解説します。
→ フォーキャスト vs バックキャスト【2つの計画アプローチ】
事業計画の作成は経営の基本ですが、より具体的で実効性の高い計画作成には専門的な知識と経験が必要です。
Nordlys合同会社では、事業計画策定から資金調達まで、経営者の皆様の事業成長を総合的にサポートいたします。
**このようなお悩みはございませんか?**
– 資金繰りが慢性的に厳しい
– 売上向上の具体的な方法が分からない
– 事業計画を根本から見直したい
– 各種公的制度の活用を検討している
– 経営全般について第三者の意見を聞きたい
Nordlysコンサルティング(https://nordlys.co.jp)では、資金調達を含む経営のコンサルティングを行っています。
**主なサービス:**
経営診断・改善提案 (特に、課題抽出)
事業計画策定支援
創業計画書の作成サポート
中期経営計画の策定支援
事業再構築計画の作成
資金調達戦略の立案
売上向上・コスト削減の具体的施策
継続的な経営サポート
月次経営コンサルティング
定期的な計画見直し
経営課題の早期発見・解決
まずはお気軽にご相談ください。
初回相談で現状分析を行い、最適な改善策をご提案いたします。
この記事は、中小企業診断士・FP技能士である筆者の実務経験をもとに作成されています。より詳しい事業計画策定支援をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。