2023年振り返り

いよいよ明日数日で今年も終わります。例年よりも暖かめな一年でしたので、先週の寒さは例年並みなのりいつもより厳しく感じました。 さて、世の中もすっかり通常モードで、忘年会の賑やかさが久しぶりに復活した年末だった気もします。久しぶりに外で飲む機会が増え、だいぶアルコールに弱くなった(歳のせいかも)のも実感しました。 今年一年を振り返ると、日常への変化の一年だったと思います。中小企業を取り巻く状況を見てみると、この数年は「コロナ」対策としてかなり手厚くさまざまな施策があった数年でした。思い起こせば2020年の持続化給付金や緊急支援金にはじまり、飲食店向けや店舗向けの給付金、事業再構築補助金や各種補助金のコロナ枠の設定、経産省だけでなく各省庁がコロナ対策の補助金・助成金を出していました。 この状況はかなり稀な状態だったと思います。なので、現政権がだいぶ絞り込んできているようにもみえます(実際にはそ ...
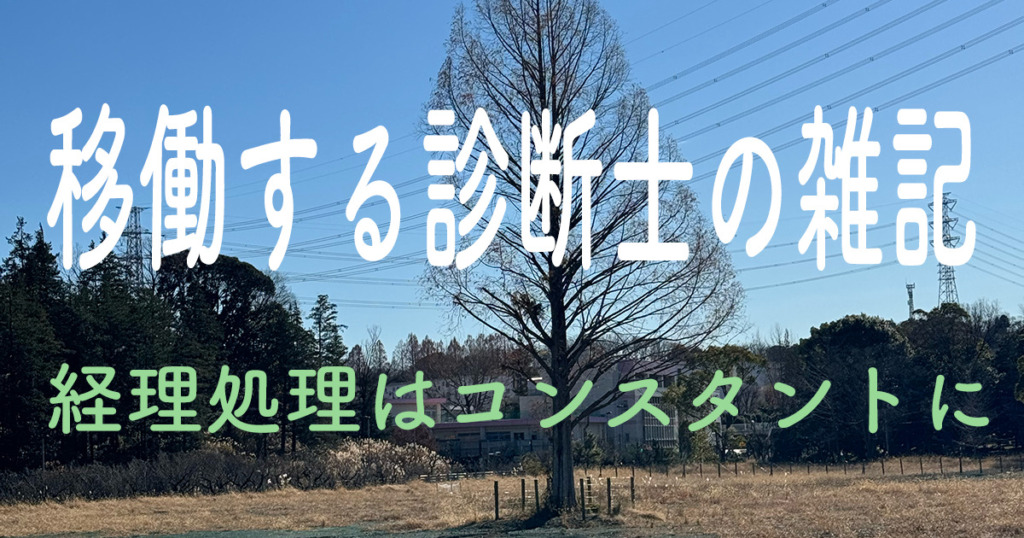
経理処理はコンスタントに
いよいよ今年もあとわずかです。 というフレーズがいろんなところから聞こえてくるようになりました。 会社員という状態から経営者という立場が変わると営業日の考え方がかなりルーズになってきていて、今年もいつもまでが営業日なのかがあやふやになってきています。(人によっては、趣味が仕事という方もいらっしゃるかもしれませんが・・・・) 個人事業の方にとっては、12月末が決算にあたります。「今年はよかった、悪か ...
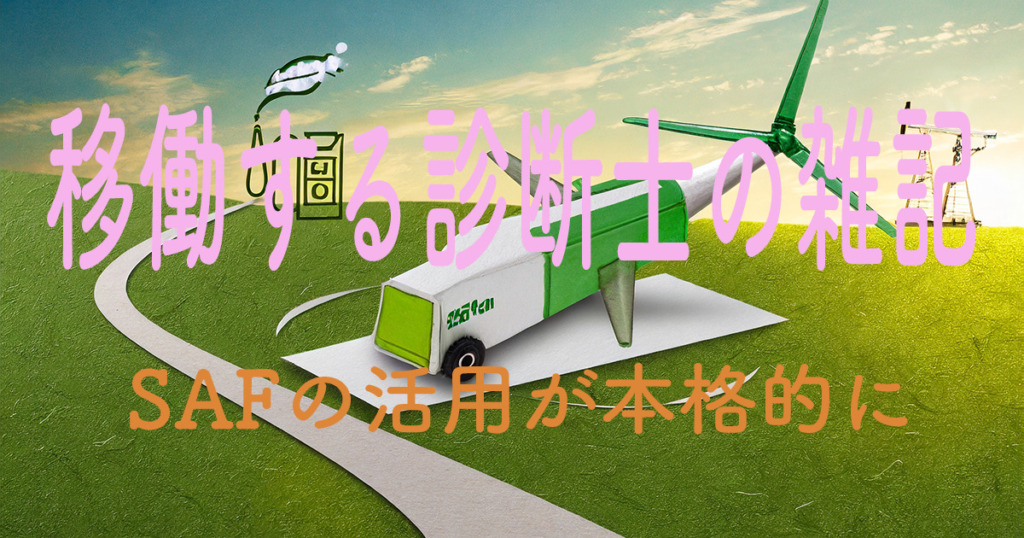
SAFの活用が本格的に
「くず〜ぃ、くずぃ、屑屋でございます。」の掛け声で始まるのが、江戸時代にあった屑屋さん。街中を回りながら、家庭で不要になった紙くず・ぼろ・古綿などを買い取ったり、逆に売ったりする商売です。落語や講談の中話の中では名脇役として今もよく登場します。 最近はだいぶ減った気もしますが「ちり紙交換」や「廃品回収」も似たようなところがあります。屑屋の場合は、直ぐにお金の必要な人が日用品を質入れするために使うこ ...
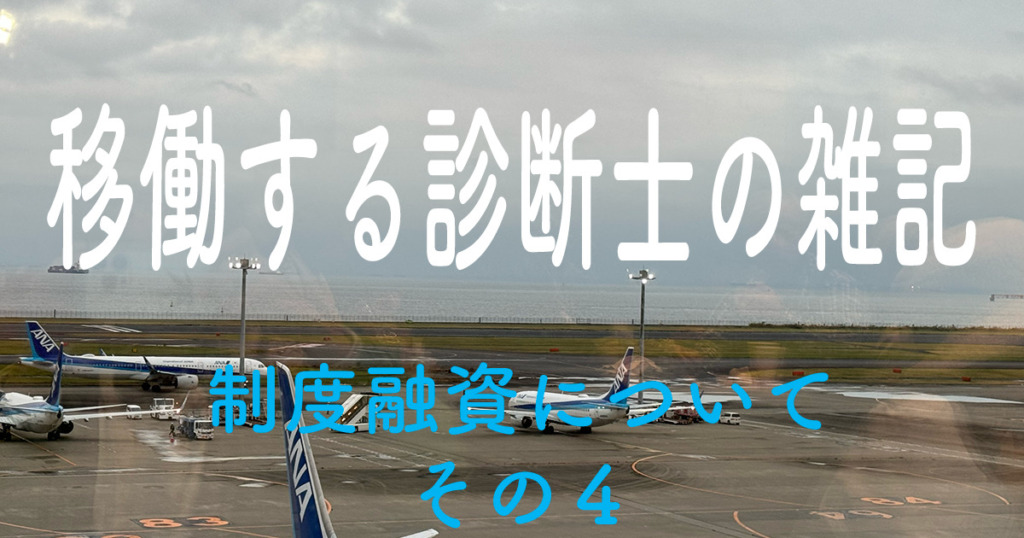
制度融資について、その4
制度融資の活用についての話のつづきです。 融資までにかかるリードタイム 制度融資は、市中の金融機関と自治体(場合によっては窓口が商工会)と保証協会で連携して行う制度です。なので、それぞれの審査が必要になります。 融資をあっせんする自治体は、その企業の財務的な部分と融資目的からこの制度の趣旨に合うかどうかを見てあっせんしています。事業者にとってはお得なこの制度ですが、金融機関も保証協会もボランティア ...
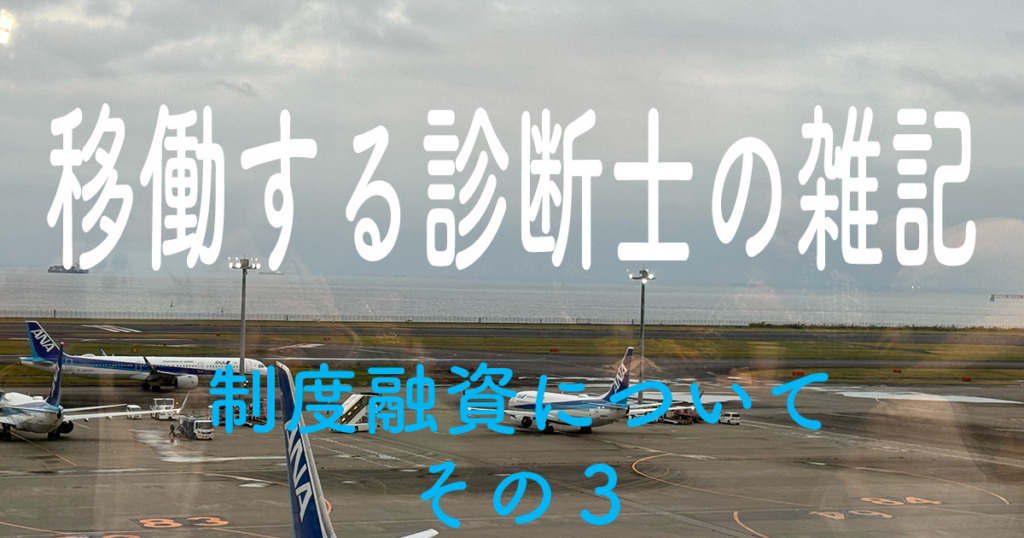
制度融資について、その3
前回からの続きで、制度融資のはなしです。 金融機関を選ぶ時の注意 制度融資は、自治体と金融機関(市中銀行)と保証協会(プロパーでも可能なケースもあるみたい)の三者が連携した制度になっています。なので、対応しているエリアが決まっています。例えば、東京都港区の制度融資であれば、保証協会は東京信用保証協会、金融機関は港区と提携しているところになります。これが、東京都武蔵野市であれば東京信用保証協会と武蔵 ...
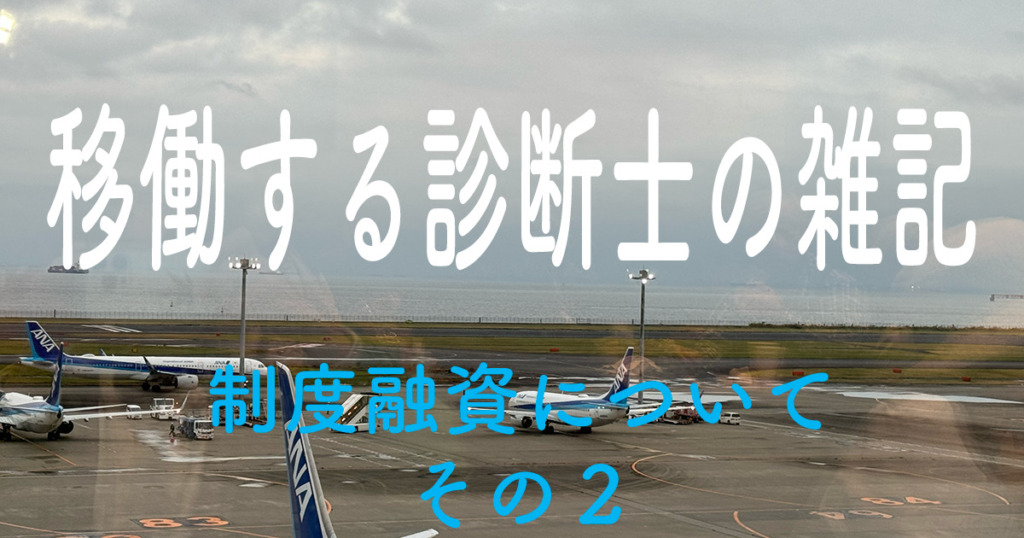
制度融資について、その2
制度融資についての話の続きです。 前回は、制度融資自体とどんなメニューがあるのかの話をしました。 制度融資の活用について 今では、数が少なくなりましたがコロナの初期、制度融資がそこまで定着していなかった頃には、「自治体が融資をしてくれる」と勘違いされて来られるケースがよくありました。こちらは異なっていて、あくまで、保証協会の保証つき金融機関融資の利用が前提です。なので、市中の銀行(都市銀行、地方銀 ...
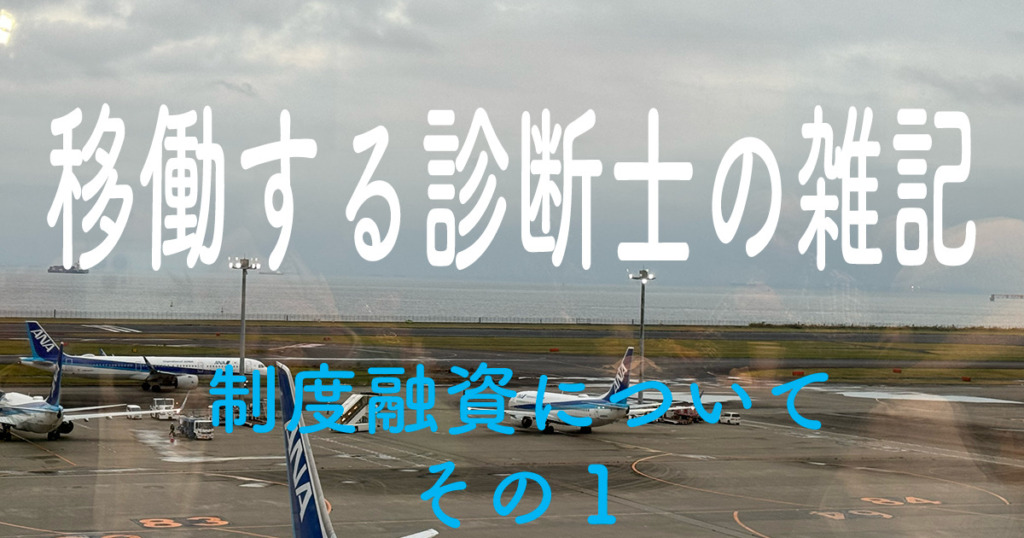
制度融資について、その1
制度融資という言葉はご存知ですか? 保証協会つきの融資を受ける場合に、自治体等の施策で利率の一部を負担してもらえる制度です。コロナ以前は知る人ぞ知るイメージのものでしたが、コロナの緊急施策として各自治体がコロナ用の融資メニュー(利息全額負担)を打ち出したことで、だいぶ一般的になりました。 コロナは落ち着きましたが、まだまだ経済状況は芳しくないため金融機関が率先して利用者にこの制度をお勧めしているよ ...